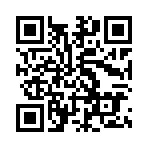2009年03月04日
白岩観音長谷寺 (群馬県高崎市)
近所の神社の参道は お稲荷様へ続く道・・・。
名もない古寺の参道は 苔むした石畳・・・。
初めて訪れたはずだけど、なぜが懐かしくもある・・・・古参道。
坂東三十三観音札所
第十五番 白岩観音長谷寺(しらいわかんのんちょうこくじ)
千三百有余年もの昔、聖武天皇の頃
開山された歴史に名高い長谷寺。
源頼朝・新田義貞・武田勝頼などの武将達の
信仰も厚かった事が記されています。
また、縁結びの由縁がある九頭竜姫をお守りとする
十一面観世音菩薩が安置されています。

「阿吽」の二字を唱える仁王様

縁結びの神様、九頭竜姫に良縁を願う
坂東十五番霊場
白岩山 長谷寺(通称 白岩観音 しらいわかんのん)
370-3332
群馬県高崎市白岩町448
Tel027-343-0349
名もない古寺の参道は 苔むした石畳・・・。
初めて訪れたはずだけど、なぜが懐かしくもある・・・・古参道。
坂東三十三観音札所
第十五番 白岩観音長谷寺(しらいわかんのんちょうこくじ)
千三百有余年もの昔、聖武天皇の頃
開山された歴史に名高い長谷寺。
源頼朝・新田義貞・武田勝頼などの武将達の
信仰も厚かった事が記されています。
また、縁結びの由縁がある九頭竜姫をお守りとする
十一面観世音菩薩が安置されています。

「阿吽」の二字を唱える仁王様

縁結びの神様、九頭竜姫に良縁を願う
坂東十五番霊場
白岩山 長谷寺(通称 白岩観音 しらいわかんのん)
370-3332
群馬県高崎市白岩町448
Tel027-343-0349
2008年01月07日
縁起ダルマの少林山 群馬県高崎市
近所の神社の参道は お稲荷様へ続く道・・・。
名もない古寺の参道は 苔むした石畳・・・。
初めて訪れたはずだけど、なぜが懐かしくもある・・・・古参道。
群馬県高崎市の1月6・7日は毎年、恒例の少林山達磨寺への参拝です。
この2日間で、約23万人が参拝するという群馬県ではお馴染みの、少林山ダルマ市。
貯まったお年玉を握りしめ、夜のお寺を闊歩する。高崎近隣の子供には恒例の縁日?

上毛カルタでお馴染みの「縁起ダルマの少林山」 朱塗りがインパクトッゥ!!

天竺ならぬ本堂までは遠い道のり

皆さんダルマを求めて遠路遥々です

長い道程を越えて今ようやく・・・・

マグマ大師ーーピロピロー・・・もとい達磨大師に敬拝を・・・
今度は平時に来て見ましょう。
追伸 下りダルマ 上りダルマの本当に存在するのか?
名もない古寺の参道は 苔むした石畳・・・。
初めて訪れたはずだけど、なぜが懐かしくもある・・・・古参道。
群馬県高崎市の1月6・7日は毎年、恒例の少林山達磨寺への参拝です。
この2日間で、約23万人が参拝するという群馬県ではお馴染みの、少林山ダルマ市。
貯まったお年玉を握りしめ、夜のお寺を闊歩する。高崎近隣の子供には恒例の縁日?

上毛カルタでお馴染みの「縁起ダルマの少林山」 朱塗りがインパクトッゥ!!

天竺ならぬ本堂までは遠い道のり

皆さんダルマを求めて遠路遥々です

長い道程を越えて今ようやく・・・・

マグマ大師ーーピロピロー・・・もとい達磨大師に敬拝を・・・
今度は平時に来て見ましょう。
追伸 下りダルマ 上りダルマの本当に存在するのか?
2008年01月04日
赤穂義士四七士石像 群馬県安中市
近所の神社の参道は お稲荷様へ続く道・・・。
名もない古寺の参道は 苔むした石畳・・・。
初めて訪れたはずだけど、なぜが懐かしくもある・・・・古参道。
新年早々、新たなコンテンツを始めてみました、その名も「古参道行脚」。
寺社に興味のある私、「信州編」 「上州編」と分けて配信していこうと思います。
第一弾は、群馬県安中市にある「赤穂義士四七士石像」への続く参道。
年末ドラマなどで、「赤穂浪士」をよく放送してますが、
地元群馬にこんな場所があろうとは・・・・知っているようでまだまだです。


この参道の向こうに何があるのか・・・ドキドキします

赤穂義士・片岡源五右衛門の下僕・元助が供養のため建立したそうです

毎年3月25日供養祭が行われているとの事

コレが落ちていたので、拾ってきました・・・・。トテモ切なく、寂しい限りです
文化財を守るために何か良い思案はないものか・・・
場所 安中榛名駅から榛名倉渕方面へ
車で3分程度
名もない古寺の参道は 苔むした石畳・・・。
初めて訪れたはずだけど、なぜが懐かしくもある・・・・古参道。
新年早々、新たなコンテンツを始めてみました、その名も「古参道行脚」。
寺社に興味のある私、「信州編」 「上州編」と分けて配信していこうと思います。
第一弾は、群馬県安中市にある「赤穂義士四七士石像」への続く参道。
年末ドラマなどで、「赤穂浪士」をよく放送してますが、
地元群馬にこんな場所があろうとは・・・・知っているようでまだまだです。


この参道の向こうに何があるのか・・・ドキドキします

赤穂義士・片岡源五右衛門の下僕・元助が供養のため建立したそうです

毎年3月25日供養祭が行われているとの事

コレが落ちていたので、拾ってきました・・・・。トテモ切なく、寂しい限りです
文化財を守るために何か良い思案はないものか・・・
場所 安中榛名駅から榛名倉渕方面へ
車で3分程度